レビュー
「先生」の廉価版を丸裸にしたら,1つの事実が見えてきた
SteelSeries Sensei[Raw]
![画像集#002のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/002.jpg) |
2011年に登場した多機能マウス「SteelSeries Sensei」(以下,Sensei)の廉価版にして,コアゲーマーが必要とする機能だけを採用したという,“生(Raw)のSensei”のポイントはどこにあるのか。今回は,Senseiだけでなく,形状が似ている「SteelSeries Diablo III Mouse」(以下,Diablo III Mouse)とも比較し,その立ち位置を明らかにしていきたいと思う。
Senseiと完全に同サイズだが重量は約13g軽い
ケーブルはDiablo III Mouseと同じく硬め
![画像集#003のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/003.jpg) |
Rubber Surfaceのほうは,さらさらとした表面になっており,指先にひっつくような感覚がない。一方,Glossy Surfaceのほうは,ベトつきやすく指紋も残るが,指先がマウスにひっつくようなグリップ感がある,といった具合だ。側面はいずれもラバーコート済みで,デザイン上の違いは存在しないため,見た目とフィット感の好みで選んでしまってまったく問題ないだろう。
![画像集#004のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/004.jpg) |
![画像集#005のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/005.jpg) |
![画像集#006のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/006.jpg) |
![画像集#007のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/007.jpg) |
![画像集#008のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/008.jpg) |
本体サイズは実測で68.3(W)×125.5(D)×38.3(H)mmとなっており,端的に言えば,SenseiおよびDiablo III Mouseとまったく同じだ。Senseiの廉価版なので当たり前といえばそれまでだが,3製品――もっといえば,Senseiのベースとなった「SteelSeries Xai」も――で金型は同じということなのだと思われる。
![画像集#009のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/009.jpg) |
この約88gというのは,Senseiの同101g(※ケーブル込みでは153g)より約13g軽く,Diablo III Mouseの同85g(※ケーブル込みでは128g)より3g重い。3製品で一番軽いのがDiablo III Mouseというのはちょっと面白いが,ともあれ,底面に液晶パネルを搭載するSenseiよりはSensei Rawのほうが確実に軽量といえる。
![画像集#010のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/010.jpg) |
![画像集#011のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/011.jpg) |
![画像集#012のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/012.jpg) |
ボタン構成はSenseiと同じく,計8個だ。左右メインとセンタークリック機能付きスクロールホイール,CPI変更用,左右サイド各2となっている。
![画像集#013のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/013.jpg) |
もっともこのあたりは「SenseiやDiablo III Mouseと変わらない」と述べたほうが正確であるようにも思われるが。
![画像集#014のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/014.jpg) |
![画像集#015のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/015.jpg) |
一方,ホイールクリックはSenseiよりも硬めで,Diablo III Mouseと同程度の硬さといった印象だ。後ほど確認するが,おそらくSensei RawとDiablo III Mouseは同じスイッチを採用しているのだろう。もっとも,“誤爆”を防止できる程度の硬さが守られているという意味において,3製品の間に違いはないともいえる程度の微妙な違いである。
次に,本体両側面で前後方向に2個ずつ並んで配置されているサイドボタンだが,こちらは実測で奥側(=メインボタン側)が約16mm,手前側(=後方側)が約19mmの長さになっていた。側面から飛び出している部分の厚みは1mm程度で,とくに出っ張りを強く感じたりはしない。
![画像集#016のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/016.jpg) |
マウスケーブルは布巻きタイプで,ケーブルの太さは実測約3mm。テストを開始して1週間が経過しても馴染まなかったほど硬い。感覚的には,「硬い」と評したDiablo III Mouseと同じくらいだ。Senseiのほうがケーブルは明らかに柔らかく,馴染みやすい。
なので,Sensei Rawの“実戦投入”にあたっては,ゲーム中の空いた時間などに揉みほぐすなどして,馴染むまでの時間を短縮したいところである。
サイドボタンに注意すれば持ち方はまず問われない
Xai&Senesi譲りの握りやすさ
![画像集#017のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/017.jpg) |
![画像集#018のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/018.jpg) |
さて,左右対称形状のマウスということで,Sensei Rawは左右両側面が大きく凹んでおり,また,2連のサイドボタンが左右両方で凹みの上に置かれるような配置になっている。それは持ち方にどういった影響を与えるだろうか。
代表的な「かぶせ持ち」「つまみ持ち」に加え,筆者独自の持ち方である「BRZRK持ち」の3パターンで試した結果が下の写真である。
ポイントは,薬指と小指側のサイドボタンを,後述するツールで無効化するかどうか。コアゲーマーが薬指と小指側のサイドボタンを積極的に使うとは思えないので,その観点から話をすると,どの持ち方でもまったく違和感はない。あえて1つ選ぶなら,個人的にはつまみ持ちがベターだと思うが,好みの問題と述べても差し支えないと思う。
どうしても薬指と小指側のサイドボタンを有効化して多ボタンマウスとして使いたいという場合は,指の位置を後方へずらすなどの対策が必要だ。BRZRK持ちだと手にかなりの負担がかかるので,つまみ持ちか,手のひらを全体的に後ろへ引いてのかぶせ持ちを選択するのが正解だろうか。
機能面はばっさり削られ
Diablo III Mouseに近い印象となった
以上,目に見えるところをチェックしてきたが,Sensei RawとSenseiの違いは重量とカバー,ホイール,ケーブルといったところ。Diablo III Mouseとはカバーとホイールくらいしか違いがないというのが筆者の実感である。
また,“中身”にも,実のところ大きな違いはない。3製品の主なスペックは表にまとめたとおりだが,トラッキング速度と最大加速度,フレームレートは完全に同じだ。SenseiはARMベースの32bitコントローラを搭載する関係で,CPIやリフトオフディスタンスのカスタマイズ性が高まっているものの,細かな部分といえば細かな部分である。
![画像集#064のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/064.gif) |
では,何が違うのか?
まずは機能面からチェックしてみよう。
SteelSeries製マウスの常として,Sensei Rawも,Windowsのクラスドライバで動作する,いわゆるドライバレス仕様だ。そして,トラッキング解像度の設定などを行いたい場合には統合ソフトウェア「SteelSeries Engine」(以下,Engine)を利用する必要があるというのも,最近のSteelSeries製マウスと同じである。
というわけで,テスト時の最新版となるバージョン2.4.1600のEngineをSteelSeriesのサポートページからダウンロードして導入後,タスクバーに常駐したEngineを開いてみた。
そろそろ“おなじみ感”の出てきたEngineのスクリーンショットを下に示したが,中央のペインに用意されるタブは「ボタン」「設定」「プロパティ」「統計」の4つだ。
![画像集#025のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/025.jpg) |
●「ボタン」タブ
![画像集#063のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/063.jpg) |
中央ペイン右上の「ボタン配置」コラム内にある表記が登録されているボタンで,その右にある「アクション」以下の文字列を「ボタン配置」コラムへドラッグ・アンド・ドロップすることで,簡単に割り当ては変更できる。
なお,Engineでは簡単なキーマクロにも対応しており,「ボタン」タブ内に用意された「ボタン配置」コラムで任意のボタン名を選択すると,中央ペインの下部にマクロ登録用の枠が出てきて,キーマクロを登録可能になる。あとは「Keypresses」の枠をクリックして,実際にマクロとして利用したいコマンドを入力すればOKだ。より細かく設定したい場合は[Advanced]ボタンをクリックして「Advanced Macro Editor」を利用することもできる。
キーマクロを使いたいという人のために注意喚起しておくと,Engineで登録したボタン配置などは基本的にマウス側へ登録されるのに対し,マクロを利用できるのは,設定に用いたEngineが常駐している環境のみとなる。
●「設定」タブ
Senseiとの大きな違いとなるのが「設定」タブで,設定できるのは,CPI設定とポーリングレート,イルミネーションの3項目。Senseiでは,SteelSeries自慢の機能群がずらりと並んでいたのだが,“Rawモデル”ということでかなりシンプルだ。
![画像集#026のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/026.jpg) 設定できる項目自体は少ないものの,CPIとポーリングレートの設定はゲームを遊ぶうえで最重要な項目なので,何度も開くことになるはずだ。トライアンドエラーをくり返し,自分にあった数値を探し出そう |
![画像集#027のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/027.jpg) こちらがSenseiの「設定」タブ。Sensei独自の「EXACT〜」系設定項目がズラリと並んでおり,一画面では表示しきれないほどになっている。ここがSensei Rawとの最大の違いということになるはずだ |
上の表でお伝えしたとおり,CPI設定は90刻み。切り替え式で2パターン登録可能だ。ポーリングレートは4段階からの選択式となる。
LEDイルミネーションは,明るさを「オフ」「最小」「中間」「最大」,明滅パターンを「常時」「ゆっくり」「中間」「はやく」とそれぞれ4段階から選択できるが,CPIごとに光らせ方を変えるといったことは行えない。その点では「SteelSeries Kana」以上に機能は絞られていることとなる。
●「プロパティ」タブ&そのほか
![画像集#028のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/028.jpg) |
標準で用意されている「Default Profiles」は「Sensei Raw Default」「Sensei Raw Fast」「Sensei Raw Slow」の3つ。CPIとLEDイルミネーションの設定が下記のとおり異なる。デフォルト設定のほかに,ハイセンシの人向けとなるSensei Raw Fast,ローセンシの人向けとなるSensei Raw Slowが用意されるイメージだ。設定の詳細は下に示した箇条書きを参照してほしい。
- Sensei Raw Default
CPI1:1620,CPI2:3240,ポーリングレート:1000Hz,明るさ:最大,点灯モード:中間 - Sensei Raw Fast
CPI1:3240,CPI2:5670,ポーリングレート:1000Hz,明るさ:最大,点灯モード:はやく - Sensei Raw Slow
CPI1:450,CPI2:810,ポーリングレート:1000Hz,明るさ:最大,点灯モード:ゆっくり
もっとも,標準のプロファイルはカスタマイズ可能で,左下ペインの「新規プロファイル」から,プロファイルを追加することもできる。「Default Profiles」はあくまで参考程度と捉えるのが正解だろう。
![画像集#029のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/029.jpg) 「統計」タブ。どのボタンをどの頻度で使っているか調べられるが,恒例のコメントになるのを断ってから続けると,利用する必要性が感じられない |
![画像集#030のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/030.jpg) タスクバーのアイコンからは「SteelSeries Settings Dialog」を開ける。ここからOS起動時の常駐設定や言語設定を変更可能だ |
Sensei RawとSensei,Diablo III Mouseを分解
中身はほとんどDiablo III Mouseと同じ
外観,スペック,機能面と見てきたが,中身はどうだろうか。今回もドライバーを片手に分解し,内部をチェックしてみたいと思う。
なお,今回は上位モデルたるSenseiと,スペックが似ているDiablo III Mouseも一緒に分解する。まずは,ソールを剥がすと姿を見せるネジを外し,カバーを外した状態で並べてみた。それが下の写真だ。Senseiは液晶パネルを搭載する関係からかケーブルが目立つのに対し,Sensei RawとDiablo III Mouseはすっきりしている。というか,Sensei RawとDiablo III Mouseは,基板の色が異なるだけでほとんど何も変わらない印象である。
![画像集#031のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/031.jpg) |
![画像集#032のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/032.jpg) |
![画像集#033のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/033.jpg) |
そこで,メイン基板に寄ってみたのが下の写真だ。基板上にプリントされている型番らしき文字列が,Sensei Rawだと「ML30B-10-1」,Diablo III Mouseだと「ML30A-10-2」と,非常に似通っているのが分かる。ちなみにSenseiは「M1112082」だった。
![画像集#034のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/034.jpg) |
![画像集#035のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/035.jpg) |
![画像集#036のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/036.jpg) |
以上を踏まえつつ,以下,写真メインでチェックしてみたい。
![画像集#040のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/040.jpg) |
![画像集#041のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/041.jpg) |
![画像集#042のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/042.jpg) |
![画像集#043のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/043.jpg) |
![画像集#044のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/044.jpg) |
![画像集#045のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/045.jpg) |
![画像集#046のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/046.jpg) |
![画像集#047のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/047.jpg) |
![画像集#048のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/048.jpg) |
![画像集#049のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/049.jpg) |
![画像集#050のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/050.jpg) |
![画像集#051のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/051.jpg) |
![画像集#052のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/052.jpg) |
![画像集#053のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/053.jpg) |
![画像集#054のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/054.jpg) |
![画像集#055のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/055.jpg) |
![画像集#056のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/056.jpg) |
![画像集#057のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/057.jpg) |
※注意
マウスの分解はメーカー保証外の行為です。分解した時点でメーカー保証は受けられなくなりますので,本稿の記載内容を試してみる場合には,あくまで読者自身の責任で行ってください。分解によって何か問題が発生したとしても,メーカー各社や販売代理店,販売店はもちろん,筆者,4Gamer編集部も一切の責任を負いません。また,今回の分解結果は筆者が入手した個体についてのものであり,「すべての個体で共通であり,今後も変更はない」と保証するものではありません。
![画像集#065のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/065.jpg) |
マウスパッド15製品でテスト
SenseiやDiablo III Mouseとの違いは出るか
ここまで仕様が近いと,先に掲載したDiablo III Mouseのレビューと同じテスト結果になるのではないかと思われるが,やはりここでも念のため,マウスパッドとの相性チェックを行っておきたい。
テスト環境とテスト時のマウス設定は順に下記のとおりだ。
●テスト環境
- CPU:Core i7-860/2.8GHz
- マザーボード:GIGA-BYTE TECHNOLOGY GA-P55A-UD4(BIOS F15)
※マウスはI/Oインタフェース部のUSBポートと直結 - メインメモリ:PC3-1333 DDR3 SDRAM 4GB×2
- グラフィックスカード:GIGA-BYTE TECHNOLOGY GV-N560OC-1GI(GeForce GTX 560 Ti,グラフィックスメモリ容量1GB)
- ストレージ:Western Digital Caviar Green(WD10EADS,容量1TB,Serial ATA 3Gbps)
- サウンド:オンボード
- OS:64bit版Windows7 Ultimate+SP1
●テスト時のマウス設定
- ファームウェアバージョン:未公開
- Engineバージョン:2.4.1600
- CPI設定:90〜5670CPI(※主にデフォルトの1620CPIを利用)
- レポートレート設定:1000Hz
- Windows側マウス設定「ポインターの速度」:左右中央
- Windows側マウス設定「ポインターの精度を高める」:無効
![画像集#058のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/058.jpg) |
なお,リフトオフディスタンスは,メーカー公称の2mmをオーバーしないかどうかを確認すべく,厚さ1mmの1円玉を2枚重ねた状態でも反応するかしないかをチェックした。その結果は使用感をまとめたコメントの最後に○/×および枚数表記を【 】書きしてみたので,合わせてチェックしてもらえれば幸いだ。
●ARTISAN 隼XSOFT(布系)
滑りがよく,快適に操作できる。【○2枚】
●ARTISAN 疾風SOFT(布系)
ちょっとした抵抗を感じるが,操作は快適に行えた。【○2枚】
●ARTISAN 飛燕MID(布系)
ザラついた感触があるものの,操作自体は快適。【○2枚】
●DHARMAPOINT DRTCPW35CS(布系)
滑りがよく,操作も快適だ。【○2枚】
●DHARMAPOINT DRTCPW35RS(布系)
抵抗感はあるが,滑りは良好で,急停止もさせやすい。【○2枚】
●Razer Goliathus Control Edition(布系)
摩擦による抵抗を少し感じるが,滑り自体は総じて良好。操作もしやすい。【○2枚】
●Razer Goliathus Speed Edition(布系)
かなり滑るが,急停止させやすく,操作に問題はない。【○2枚】
●Razer Ironclad(金属系)
滑り自体は控えめながら,操作はしやすい。【○2枚】
●Razer Scarab(プラスチック系)
プラスチックと擦れる感触はある。ただ,操作は行いやすい。【○2枚】
●Razer Sphex(プラスチック系)
少しの抵抗を感じるものの,操作自体は良好だ。【○2枚】
●Razer Vespula(プラスチック系,両面)
両面ともに滑りはよく,快適に操作できる。【○2枚】
●SteelSeries 9HD(プラスチック系)
ザラザラとした抵抗感は少しあるが,快適に操作できた。【○2枚】
●SteelSeries QcK(布系)
滑りがよく,快適に操作可能。【○2枚】
●ZOWIE G-TF Speed Version(布系)
滑りがよく,操作も快適に行える。【○2枚】
●ZOWIE Swift(プラスチック系)
擦れる感触こそあるが,操作に悪影響はない。快適だ。【○2枚】
以上,定評あるADNS-9500系ということで,大きな破綻はない。もっといえば,SenseiやDiablo III Mouseとも大差はない印象だ。
なお,Sensei Rawで直線補正の有効/無効は切り替えられないが,試してみた限り,直線補正は多少なりとも有効になっているようだった。
![画像集#059のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/059.jpg) |
![画像集#060のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/060.jpg) |
「Senseiの下位モデル」という扱いがいいのかはさておき,完成度は上々。扱いやすいマウスだ
テストしていて気になったのは,Sensei RawのCPIが90刻みであること。たとえば普段600CPIでプレイしているゲームがあったとして,それをSensei Rawで設定しようと思ったら540CPIか630CPIを選択し,ゲーム側で微調整しなければならないのだ。
![画像集#061のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/061.jpg) |
ただ,多くのゲーマー向けマウスが100CPIや200CPI刻みの設定を採用しており,ゲーマー側がそれに慣れてしまっている現実もあったりするので,Sensei Raw用に頭と操作感を切り替えるのには慣れが必要かもしれない。
また,これをSenseiの廉価版と位置づけていいのかという疑問は,どうしても残る。Senseiというマウスにおける最大のアピールポイントであるカスタマイズ性がほぼ完全に奪われたことによって“Diablo III Mouseの派生品”になってしまっているわけで,Sensei Rawという製品名は,名が体を表していない感がどうしても拭えない。1刻みのCPI設定など,内面的なSenseiらしさがもう少し残っていればよかったのだが。
![画像集#062のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/062.jpg) |
SteelSeries Sensei[Raw] Rubberized BlackをAmazon.co.jpで購入する(※Amazonアソシエイト)
SteelSeries Sensei[Raw] Glossy BlackをAmazon.co.jpで購入する(※Amazonアソシエイト)
SteelSeries Sensei[Raw]製品情報ページ
- 関連タイトル:
 SteelSeries
SteelSeries
- この記事のURL:
Copyright 2010 SteelSeries Aps









![「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/001.gif)

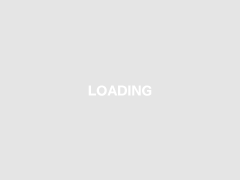





![画像集#019のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/019.jpg)
![画像集#020のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/020.jpg)
![画像集#021のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/021.jpg)
![画像集#022のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/022.jpg)
![画像集#023のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/023.jpg)
![画像集#024のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/024.jpg)
![画像集#037のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/037.jpg)
![画像集#038のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/038.jpg)
![画像集#039のサムネイル/「SteelSeries Sensei[Raw]」レビュー。Senseiの廉価版は「BlizzardとコラボしていないDiablo III Mouse」だった!?](/games/037/G003732/20120809037/TN/039.jpg)
