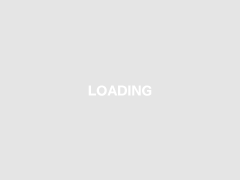ニュース
台湾市場の現状と開発パートナーとしての特徴を探る,アジア太平洋ゲームサミットの講演レポート
 |
はたして台湾のゲーム市場にはどのような特徴があり,またそこで実際に活動している日本のパブリッシャやデベロッパは台湾市場をどのように見ているのだろうか。TGSはTGSでも台北ゲームショウの一環として,東京ゲームショウと同日程で開催された「アジア太平洋ゲームサミット」での講演とパネルディスカッションの模様をお伝えしよう。
 |
世界有数の大きなゲーム市場,台湾
最初に,台北国際ゲームショウのマーケティング総監であるSally Tsai氏が,台湾のゲーム市場を概説した。
台湾は総人口2344万人に対し,ネットプレイヤーは1869万人,スマートフォンの台数は3260万台となっている。都合,すべての国民が1台以上のスマートフォンを持っているという計算になる。
ゲームプレイヤーの人口は,2015年には765.6万人で,2016年には813.3万人に増加する見込みとなっている。最も人気があるのは携帯ゲームで,473.5万プレイヤーとなっているが,PCでのオンラインゲームが2番人気で312.7万人とハードコアなゲーマー層の厚さを感じさせる。
 |
 |
市場規模としては,2015年段階で4203.9億元(2016年9月17日現在のレートで約1兆3千億円)だ。日本は8兆円規模だが,人口比で考えると日本市場に肉薄する数値となることが分かるだろう。市場は年5%規模で増大しており,2019年には5302.4億元に到達する見込みだという。
以下,細かく各分野の市場規模を見てみよう。
オンラインゲーム(PC)の市場規模は2015年で1192.7億元で成長率は年1〜2%と堅調だ。
ブラウザゲームは494.7億元と規模がやや小さく,こちらも年1〜2%の成長となっている。
モバイルゲームは2430.8億元と他を圧倒する規模を有し,成長率も高い。
先にも述べたように台湾のゲーム産業における収益の総合計は世界15位だ。モバイルを見ると,App storeで売上10位,Google Playで4位と,高い購買意欲を示す市場が見て取れる。
 |
市場の特徴としては,「開かれた市場である」点が最も注目される。
例えば中国市場の場合,規模は大きいが,モバイルゲームの売上ランキングを見ると中国企業がベスト10のうち9社を占めている(これには国策の影響もある)。
日本市場のランキング傾向も同様で,ランキングベスト10のうち9社が日本企業だ(こちらはゲーマーの消費習慣が日本独特であることによる影響が強い)。
韓国のランキングは比較的多様性があるが,それでも上位3位は韓国のデベロッパが占めている。
これらと比べると台湾のランキングは極めて多種多様で,さまざまなゲームにチャンスがあることが分かる。
 |
また,しばしば「台湾のゲーマーは日本のアニメや漫画的な表現を好む」という傾向が語られるが,これについてもアンケート結果が提示された。
台湾ゲーマーが好きなゲームのビジュアル表現を比較すると,26%が「日本のアニメ風」を好む(ランキング1位)。ここに「かわいい風」を加算すると,日本で一般的に用いられているビジュアルを最も好むプレイヤーが全体の38%を占めていることが分かる。
 |
台湾のゲーマーが好むゲームのジャンルや支払い傾向(※以下,支払いを課金と呼ぶ)にも,特徴が見られる。
オンラインゲームではRPGが圧倒的で,2位はシューティング。プレイヤーの課金率は実に80%に及び,女性プレイヤーでも70%が課金するというコアな市場となっている。支払い手段はコンビニ販売のギフトカードが最も人気がある。
ブラウザゲームの場合,RPGとシミュレーションが強いが,課金率は43.1%と落ち込み,女性の課金率は33.1%まで落ち込んでしまう(とはいえ世界的に見ると高比率であるのは言うまでもない)。支払い方法としてはコンビニのギフトカードが強いが,クレジットカードによる支払いや,携帯を使ったマイクロペイメントも目立つ。
モバイルゲームでは,RPGとパズルが非常に強く,カードゲーム,シミュレーションと続いていく(RPGが強いというのは,世界的に見ると特徴的なことだ)。課金率は56%とブラウザゲームより高く,支払手段はクレジットカード払いが45.6%と非常に高い水準を示している。
トータルで見ると,男性ゲーマーの60%が課金プレイヤー,女性ゲーマーの40%が課金プレイヤーとなっており,課金率は非常に高い市場といえる。
 |
 |
ゲームのマーケティングでは,SNSの影響力が大きい。
台湾ではFacebookのアクティブプレイヤー数が1300万人/日で,浸透率は75%と圧倒的だ。またLINEも登録プレイヤーが1500万人を超えており,64%とFacebookに迫る浸透率を示している。
とはいえ台湾ローカルなSNSや情報サイトの影響力も大きく,ゲームの情報だと巴哈姆(バハムート)はとくに有名だ。
これら以外にも屋外での掲示型広告などは盛んに行われており,台北ではビルの壁面がゲームの広告で覆い尽くされることも珍しくない。
結果として,台湾におけるマーケティングコストは増大傾向にある。
台湾5大メディアの広告量を見ると,さまざまなジャンルで軒並み成長率が鈍化もしくはマイナス成長に落ち込んでいるなか,IT関連の広告は前年比27.9%の急激な伸びを示している(広告費用は合計で23.76億元)。
 |
最後に台湾市場のもう一つの特徴として,ゲームショウの影響の大きさがある。
台北ゲームショウには40万人が参加し,140万人がストリーム配信を見ている(2015年の東京ゲームショウは26.8万人が参加)。また台北ゲームショウはB2Bにも強く,22カ国から2000社のバイヤーが訪れ,1000件を超える商談が成立している。
同時に,併催されているアジア太平洋ゲームサミットではさまざまな講演が行われ,合計50セッションに2000人を超える来場者が参加したという。
 |
台湾ゲーマーは飽きやすい? 台湾市場を巡るパネルディスカッション
続いて,台湾で活躍するデベロッパの代表者によるパネルディスカッションが開催された。
登壇したのは大崎敦士氏(ミクシィ 海外運用部部長),Sky Lin氏(Wargaming Head of business development, asia),永田博丈氏(ソネットエンタテイメント台湾 CEO),劉昱昌氏(FUN YOURS Technology 副社長),椎葉忠志氏(Aiming 代表取締役)の5名だ。モデレーターはJesse Wu氏(台北国際ゲームショウ事務局 最高経営責任者)が務めた。
 |
永田氏はこれに対し,台湾ゲーマーが日本のアニメに馴染みがあることを示し,ほかの地域に比べると成功率が高いことを挙げた。とはいえ,実際に台湾のゲーム売上げランキングを見ると上位は中国系デベロッパが占めており,「プレイヤーは多いが売上が厳しい」という状況に陥りがちであるとも指摘した。
また,台湾での事業展開は,やはり日本と台湾でゲームの作り方は異なっているので,日本のやり方をそのまま持ち込むと失敗しやすいという。現地の肌感を大切にし,現地のテンポや感覚とズレるような方針を採らないことが重要だと語った。
Lin氏は,台湾の経済が健全で,国民の所得が高いことに注目する。東南アジアのほかの地域より,台湾のほうが経済的に安定したマーケットであるというわけだ。
また「いくら台湾市場が多様性を持つオープンなマーケットといっても,軍事や歴史をテーマにしたゲームはヒットしないだろう」という予測が語られることはあったが,実際にWorld of Tanksを台湾でリリースすると,台湾のゲーマーはすぐにこれを受け入れたのだという。
劉氏は,台湾市場を「島型の市場」と定義する。世界中からプロダクトが流れ込んでくることに対して,消費者が慣れている市場という意味だ。
とはいえ,そんな台湾市場においても,ローカライゼーションの重要性は変わらない。また宣伝するポイントを見つけるのが大事で,とくに台湾では「皆が遊んでいる」ということによる影響が大きいため,そこを上手に利用していくべきだと指摘した。
 |
続いては「台湾にはたくさんの日本製ゲームがあるが,ローカライゼーションにおいてどのような工夫をしたのか。あるいは開発時からローカライゼーションを意識したということはあるか」という質問だ。
椎葉氏はここで,「台湾のゲーマーは飽きっぽい」という指摘をする。台湾ゲーマーは全体的にモチベーションが高く,また情報共有が極めて速いので,新しいゲームが出るとすぐにそちらに移動してしまうというのだ。実際,ラグナロクオンラインが全盛だった時代,台湾でもラグナロクオンラインは大ヒットしたが,他国ではまだまだオンラインゲームトップの座に君臨していた時期でも,台湾ではすでに首位から陥落していたという。
このため,プレイヤーを飽きさせないために,「剣と魔法のログレス」では日本で2年かけてサービスしてきたコンテンツを,半年でつぎ込むような体制をとったのだという。もっともゲームシステムの根底を変化させるようなことはしておらず,あくまで運営のテクニックとしてコンテンツ密度を上げることを意識したということだ。
大崎氏もまた,台湾のゲーマーが「情報の調査と共有が極めて速い」ことを指摘する。モンスターストライクの場合,日本で先にサービスされたコンテンツの情報があっという間に台湾で共有され,台湾でリリースされる前の段階で,いわば「情報的には攻略済み」になっていることがあるという。
これに対しては,台湾独自のコンテンツを導入するほか,ゲームの仕様にも台湾独自の仕様を採用するといった施策を行っているとのことだ。
 |
次は,同じローカライズでも,「マーケティングにおけるローカライズについて」である。
永田氏もまた,「台湾のプレイヤーは飽きっぽい」と認め,「日本での情報を素早く翻訳してシェアするオピニオンリーダーがいるため,情報の出回りが非常に早い」と語った。結果として,台湾オリジナルの要素も欠かせないという。
マーケティングという点では,台湾ではオフラインでの広告にもまだある程度の効果が見込めるという。とはいえプロモーション攻勢をかけ続けるだけでは限界がある。重要なのはコアプレイヤーの支持を集め,これを維持することであり,そのためには生放送などでプレイヤーと運営が直接向き合っていくような施策が必要であると語った。
Lin氏もまた,コアプレイヤーの獲得と維持の重要性を強調する。Lin氏がとくに注目するのは,台湾における「皆が遊んでいるゲームが注目される」の逆作用,つまり「一部のプレイヤーが離脱を始めると,そのゲームからプレイヤーが離脱するトレンドができてしまう」ことだという。
また,台湾プレイヤーは新しいものをとくに好む――つまり飽きっぽい――ので,広告素材にしても1週間を一つの区切りとし,事前になるべく多くの素材を用意しているという。同様に,一気に盛り上がる話題を提供することには大きな効果があるため,均等に広告予算を配分するよりは,一時期に集中運用して「台湾の生活に密着した,何か大きなこと」をしたほうが効果的だと述べた。
 |
さて,日本企業が台湾でゲームを開発・運営するとなると,現地でパートナーを組む企業が重要となる。ここにおいて「パートナー企業をどのように探し,誰を選ぶべきか」というのが次の議題だ。
大崎氏は,「何よりも自分達の作りたいものに共感してもらえるかどうかが重要」と語る。ミクシィは「友達や家族で遊んで盛り上がるゲーム」を目指しているが,この目標を共有できるパートナーでなくては,事業はうまくいかないというわけだ。
椎葉氏は「自分の場合は,台湾で見つけたパートナーが誠実で良い人ばかりというラッキーに恵まれた」としつつも,基本的には日本におけるパートナー探しと変わることはないと語った。
AimingはFUN YOURSをパートナーとしているが,これには椎葉氏自身がFUN YOURSの作品の熱烈なファンであったという背景があるという。そして台北ゲームショウでFUN YOURSの劉氏に出会い,「いつか一緒に仕事をしましょう」と提案したのが馴れ初めというわけだ。
そのうえで椎葉氏は,モバイルオンラインゲームはリリースして終わりではなく,長くサービスしていく必要があることを強調する。ここで成功するためには,パートナー企業の数字的な業績がどうこうというだけでなく,彼らが作ったゲームを遊び,また社員らと一緒に食事をするなどして,長期間に渡って一緒にやっていけるかどうかを確認していく必要があると語った。
とはいえ,もちろん,そういった「意気込み」だけで良い協業ができるわけではない。椎葉氏は近年におけるスマートフォンの更なる技術向上を受け,グラフィックスに要求される水準がさらに一段階上がったことを指摘する。このため「2015年くらいまでであれば,台湾で開発された『これはちょっと日本向けではないかな』と思うようなグラフィックス水準のゲームを日本にそのまま持ってきても大丈夫だったが,2016年は日本向けに高いレベルでグラフィックスを作れるデベロッパでないと一緒にうまくやっていくのは難しい」という。
 |
続いて,「パートナー企業としての,台湾企業の強みは何か」という質問だ。
永田氏は大前提として,台湾のエンジニアが優秀で,かつコミュニケーションしやすいという点を指摘する。台湾人と日本人はメンタリティ的に近いところも多く,友達づきあいするのが簡単だという。
しかしながら,良い友人と,良い仕事のパートナーとでは,求められるものは自ずから異なる。このため,「日本人から台湾人を見ると,仕事が雑で適当,後先考えないという印象を受けがち」「台湾人から日本人を見ると,仕事が遅く,あまりに保守的で,判断を回避したがるという印象を受けがち」という差異が生まれやすいという。とはいえ,この点については,「そういった反応が発生しがちだというのを前もって理解しておくことで,問題は大きく緩和される」という。
Lin氏は永田氏の意見に同意したうえで,台湾人は1983年のスーパーファミコンをゲームキャリアのスタート地点にしているゲーマーが多く,1990年以降の経済発展もあって社会にゲーム文化が根付いている点を指摘して「30〜40代の台湾人がゲーム慣れしていることは大きなメリット」だと語った。
劉氏もまた,開発者にファミコン世代が多いことを利点として挙げた。台湾でゲーマーとして育ってきた開発者は,ゲームに対する認識や習慣が,日本の開発者のそれに近いのである。結果,ゲームに関するコミュニケーションがたやすく,またゲームについての知識も豊富な開発者が多いという。
同様に,台湾では17〜18時に日本のアニメが放映されていることもあって,日本の漫画やアニメに慣れ親しんでいる開発者も多い。このため美術制作の面においても,より日本のマーケットにフィットしたものを作りやすいというのは,大きな利点であるとした。
 |
最後に台北国際ゲームショウに対する意気込みが聞かれたが,これについてはむしろ最初に台湾のゲーム市場を解説したSally Tsai氏の言葉のほうが,日本の読者にとっては有益なので,これを引用しておこう。
「日本と台湾の距離は近く,旅行しようと思えば日帰りでの旅行も可能です。2017年の台北国際ゲームショウは来年の1月20日〜24日に開催されますが,シーズン的にも温泉が気持ちのよい時期ですので,日本のゲーマーもぜひ訪れてみてください」
 |
 |
- この記事のURL: