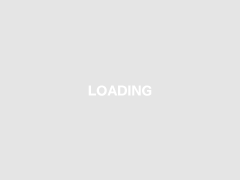ニュース
[GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?
![画像ギャラリー No.002のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/002.jpg) |
ゲームにおけるハプティクスとは
![画像ギャラリー No.003のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/003.jpg) |
ピエゾ素子(圧電素子)や,筋電気刺激(Neuromuscular Electrical Stimulation,NMES),GVS(Galvanic Vestibular Stimulation,直流前庭電気刺激)素子を使うものなど,さまざまな刺激をユーザーに与えて,ゲームに対する没入感を高めようとする試みが行われている。
ただ,製品価格や安全面を配慮すると,ゲームユーザー向けハプティクスは,振動系の素子が今でも主流だ。
同じ振動系ハプティクスデバイスでも,任天堂がNintendo Switchの標準ゲームパッド「Joy-Con」に導入したリニアモーター系振動素子(Linear Resonance Actuator,LRA)は,高い周波数の振動を再現できるのが革新的だった。事実上,ゲーム向けハプティックスの解像度を上げることに成功したことで,これまでのロータリーモーター系回転振動子では,再現できなかった「硬いもの同士が衝突したような高周波の振動」も再現可能としたのだ。
このLRA素子の振動機能を,「HD振動」と命名した任天堂のネーミングセンスは,なかなかのものだと思う。
LRA素子の発展形といえるのが,PlayStation 5が標準ゲームパッド「DualSense」に採用した広帯域リニアモータ系素子(Wide band Linear Actuator,WLA)だ。WLAは,再現可能な振動の周波数を,LRAよりも広げたものと考えていい。LRAに比べると,振動のパワーも上がっているので,簡易的な力覚表現が可能になった点も,特筆すべき進化点と言える。
![画像ギャラリー No.004のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/004.jpg) |
ミライセンスは,こうしたハプティクス技術を,ハードウェアとソフトウェアの両面から進化させる技術を研究開発している企業だ。
![画像ギャラリー No.005のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/005.jpg) |
ミライセンスが提唱する「3Dハプティクス」では,力覚(Force),Pressure(圧力),Tactile(触感)を「3原触」(3 Primary Touch Feeling)と定義する。これらを組み合わせて,ゲームに有用なハプティックスを提供しようと考えているわけだ。
![画像ギャラリー No.006のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/006.jpg) |
GDC 2025におけるブース展示とセッションのメインテーマとして,ミライセンスが訴求していたのは,ソフトウェアソリューションのAMPTIX(関連リンク)である。
AMPTIXは,ハプティクス表現のオーサリングソフトと,オーサリングソフトで制作したハプティクス表現を,各ゲームプラットフォームのコントローラで再現するためのランタイムミドルウェアで構成されるものだ。
![画像ギャラリー No.007のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/007.jpg) |
AMPTIXのオーサリングソフトでは,ゲームの進行過程で発生する,さまざまな事象に対するハプティクス表現を,以下に示す4つのアプローチから製作できるという。
- Force(力覚)
- Tactile(触感)
- Auto Amp
- Stream
![画像ギャラリー No.008のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/008.jpg) |
Auto AmpとStreamは,音声や楽曲から振動エフェクトを作るような,オーディオ→ハプティクスのコンバータ的なものに相当しており,他社製品にも存在している。そこでセッションでは,AMPTIXのオーサリングソフト独自の要素として,力覚と触感のハプティクス表現を解説していた。
振動子が作り出す力覚表現とは?
力覚とは,押したり引いたりといった動きを感じるハプティクス表現だ。最もイメージしやすいのは,PS5のDualSenseにおける「アダプティブトリガー」のような,「グググ」という感じでユーザーの手や指に力をかけてくるような表現だろう。
ただ,AMPITIXでは,やや趣の異なる力覚表現が行える。具体的には,ゲームパッドが手から奥に逃げだそうとするような表現や,逆に自分を押してくるかのような表現だ。
「振動素子で,どうやってそんな表現が実現できるのか」と,ピンとこない人も多いだろう。リニアモーター系振動子が実現する直線反復運動系の振動では,反復振動の一方向だけ加速度を強めて,逆に反対方向は加速度を弱めてやることで,強い加速度で振動した方向に引っ張られるような力を感じてしまうのだ。精神物理学的な錯覚である。
たとえば,前後に振動するリニアモーター系振動子で,前方向には強い加速度で,後方向には弱い加速度で振動させると,それを握っている人は,前に引っ張られるよう錯覚するのだ(関連記事)。
PS5のDualSenseには,左右のグリップそれぞれにWLAを組み込んでいる。そこで,左右のWLAで非対称加速度な反復運動制御を行って,一定方向に力覚を感じさせれば,そのコントローラが前や後ろに引っ張られるように感じる。左右のWLAにそれぞれ逆方向の力覚を与えれば,ゲームパッドが回転しているように感じさせられるのだ。
振動表現であることに違いはない。だが,振動のさせ方を工夫することで力覚が発生する錯覚を応用すると,振動表現の中に力覚表現を紛れ込ませることすらできるようになる。
AMPTIXのオーサリングソフトにいて力覚系のハプティクス表現を制作する場合は,次に示すタイムライン編集画面で行う。
![画像ギャラリー No.009のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/009.jpg) |
実際の編集画面を撮影したものも掲載しておこう。紫色と水色の折れ線グラフは,それぞれがゲームパッドの左力覚出力,右力覚出力に当たる。
![画像ギャラリー No.010のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/010.jpg) |
編集画面には,音声波形のような水色の線が見える。これは,リファレンス用として,ショットガンの引き金を引いたときの発射音を読み込んだ状態だ。発射音に続いて,銃のメカ部分の作動音や,薬莢をはじき出す音が鳴るというシーケンスとなっていた。
画面では,水色と紫色の折れ線グラフのようなものも見えるが,これは,それぞれ左右のWLAに与えた力覚を表す。折れ線グラフが上方向へ移動しているときは,奥方向への力覚。逆に下方向への移動は,手前方向の力覚を表す。つまり,銃を発砲した直後に時間差で反動がやってきて,奥→手前と微動する感じのハプティクス効果を作り込んでいるのが見て取れる。
なお,こうした力覚が表現できるのは,WLAやLRAタイプのリニアモーター系振動素子に限られる。ロータリーモーター系振動子の場合は,力覚演出を省略した振動主体のハプティクス表現へと自動変換されるという。
AMPTIXのオーサリングソフトで制作したハプティクス表現は,下位ハードウェアに対してのフォールバックにも対応しているわけだ。
触感をビジュアルに設計できる
![画像ギャラリー No.011のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/011.jpg) |
先にミライセンスが提唱する「触覚の3原触」の概念を紹介したが,AMPTIXのオーサリングソフトにおける触感表現は,Fine(細かさ),Sharp(鋭さ),Random(ランダム性),Intensity(強度),Pan(左右定位)という5つのパラメータで表す。
基本的には,FineとSharp,Randomの組み合わせで作り,IntensityとPanは,配置や調整のためのパラメータという扱いだ。
![画像ギャラリー No.012のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/012.jpg) |
Tactileの編集画面では,5つのパラメータを設定して最終的な触感表現を決定する。面白いことに,FineとSharp,Randomの値は,編集画面では図形で表現しており,作成している触感を視覚的にイメージできるようになっている。これは,ミライセンスの特許技術だそうである。
GDC 2025のEXPO会場のミライセンスブースでは,AMPTIXのオーサリングソフト上で5つのパラメータを変えると,図形がどう変化するかを試せた。写真で紹介しよう。
Fineは,触感のきめ細かさを表すもので,振動周波数の高低に近いイメージだ。編集画面では,図形の大小で高低を表す。
![画像ギャラリー No.013のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/013.jpg) |
![画像ギャラリー No.014のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/014.jpg) |
Sharpは,低いとツルツルとした,高いとチクチクとした触感を感じるパラメータだ。パラメータが小さければサイン波(緩やかな振幅変化),高ければ三角波やノコギリ波(急峻な振幅変化)になるようなイメージとなる。編集画面では,図形の輪郭のトゲトゲ具合で示す。
![画像ギャラリー No.015のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/015.jpg) |
Randomは,各パラメータに対してノイズを与えるものだ。パラメータが小さいければノイズなし,大きい値にすれば,ランダムな上下変動が大きくなる。
Intensityは,触感の増幅度を決定するという。サウンドで例えれば,音量調整のようなものだ。ハプティクス表現の強弱を,効果音の音量の強弱と連動させれば,遠近感を演出できる。
Intensityの高低は,編集画面では寒色や暖色として表現している。サーモグラフィとかヒートマップのようなイメージだ。
![画像ギャラリー No.016のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/016.jpg) |
![画像ギャラリー No.017のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/017.jpg) |
最後のPanは,制作した触感を左右どちらに配置するかを決める。サウンドでいえば,左右定位(パンポット)を設定するものだ。ハプティクス機能を持つ多くのゲームパッドでは,振動素子を左右(※グリップ内)に配置しているので,作り出した触感を,どちらの振動子で再生するのかを決定する。編集画面では,図形が出現する左右バランスで示す。
AMPTIXのオーサリングソフトで制作したさまざまなハプティクス表現は,PCや,主要なゲーム機向けのゲームで再生される。その制御を司るのが,AMPTIXのランタイムミドルウェアだ。ゲーム進行に合わせてのハプティクス再生は,ランタイムミドルウェアが提供する専用APIを使うか,主要ゲームエンジンに対応したプラグインを利用するかのどちらかを選べる。
実際,多くのゲームにおいては,効果音やBGMなどの音響効果や,グラフィックスのエフェクト描画タイミングに連動させて,ハプティクス表現を再生するだろう。
たとえばドライビングゲームであれば,発進や加速,減速や落下といった状況に応じて,事前に作り込んだハプティクス表現を再生できる。
![画像ギャラリー No.018のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/018.jpg) |
走行中に路面状況が刻々と変化していくのであれば,それに応じてハプティクス表現の再生もミックスされていくそうだ。
![画像ギャラリー No.019のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/019.jpg) |
ダイナミックなゲーム進行だけでなく,あらかじめ時間進行に沿ってイベントやドラマが展開するスタティックなムービーシーンにおいても,映像や音響の展開に完全にシンクロさせて,作り込んだハプティクス表現を再生することもできる。
![画像ギャラリー No.020のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/020.jpg) |
上のスライドは,まさにそうしたハプティクス表現を埋め込む編集画面だ。編集画面の右下は,イベントのムービーシーンを再生するプレビュー画面で,中央にある水色の波形は,ムービーで再生するすべての音響要素を示す。ハプティクス表現の制作者は,ここで映像と音響を見ながら,力覚エフェクトや触覚エフェクトの設定を埋め込んでいけるわけだ。
![画像ギャラリー No.021のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/021.jpg) |
ハプティクス表現の制作概念を変えるミライセンスのAMPTIX
![画像ギャラリー No.022のサムネイル画像 / [GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/022.jpg) |
とくに,実際に触れて面白かったのは,一般的な振動表現に,力覚表現がオーバーレイされて加わったときの,ハプティクス表現のリッチさだ。次なる新世代ゲーム機では,どの程度かは分からないが,ハプティクス表現についても進化することだろう。それに合わせて,ミライセンスのAMPTIXによって表現できるハプティクス表現も,さらに高次元なものになるに違いない。
ミライセンス 公式Webサイト
4Gamerの「GDC 2025」記事一覧
- この記事のURL:







![[GDC 2025]ゲームパッドが引っ張られたり回転したりする触感を作れる,ミライセンスの3Dハプティクス技術「AMPTIX」とは?](/games/999/G999902/20250327017/TN/001.jpg)