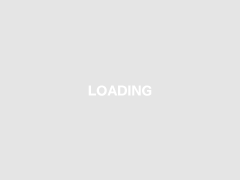業界動向
Access Accepted第822回:UbisoftがTencentの巨額資本を受けて子会社設立。創立からの歴史を振り返り,その狙いを考える(後編)
 |
前回の当連載は,Ubisoft Entertainmentの創立からの歴史を辿っていくだけで,だいぶ長くなってしまった。後編では,同社がどうして今のようになったのかという現状を深掘りしながら,ゲーム業界の巨人であるTencentから巨額の投資を受けて子会社を作ることになった理由,その意義を考えてみたい。
巨大化したパブリッシャに蔓延したハラスメント問題
Ubisoft Entertainmentが,Tencentから11億6000万ユーロ(約1890億円)もの出資を受けて,「アサシン クリード」「ファークライ」「レインボーシックス」という看板ブランドの開発を統括する子会社を設立することをアナウンスしたのは,「アサシン クリード シャドウズ」のリリースから8日後(日本時間2025年3月28日)のことだ。
前回の当連載(リンク)でも紹介したように,来年で創立40周年を迎えるフランスの古豪パブリッシャが存続のために“重要な経営判断”を行った。
 |
前回の補足をしておきたいが,新型コロナウイルス感染症が発生した当初は巣ごもり需要に沸いていた大手パブリッシャとは異なり,Ubisoft Entertainmentの株価は2018年8月をピークに下落し続けている。大手メディアVivendiによる敵対的M&Aを防いだ当時,すでに1万6000人という従業員を50社近いスタジオに擁し,他社より多くAAA級タイトルをリリースしていたものの,大ヒットと呼べるほどの“AAAA級”が生み出されることはなく,雇用者あたりの収益は低かった。
さらに「#MeToo運動」の高まりによって,Activision Blizzardの労使問題が大きな話題になった頃,Ubisoft Entertainmentでも同様の事態が起きていた。同社のナンバー2,Chief Creative Officer(CCO)であるセルジュ・アスコエ(Serge Hascoët)氏が辞任し,編集/クリエイティブサービス担当副社長のトマス・フランソワ(Thomas François)氏,そして上級幹部だったギヨーム・パトゥルクス(Guillaume Patrux)氏が重大な不正行為により解雇された。
また,同社初のヒット作「Rayman」シリーズの生みの親であるミシェル・アンセル(Michel Ancel)氏に加えて,「アサシン クリード IV ブラック フラッグ」から「アサシン クリード オリジンズ」まで主導したクリエイティブディレクターのイズマエル・アシュラフ(Ashraf Ismail)氏といった,開発チームの重要メンバーも同社を去っている。
1988年から同社を率いるイブ・ギルモ(Yves Guillemot)氏ら,Ubisoft Entertainmentの創業者であるギルモ兄弟は直接的な行為を追及されていないが,その責任は今も問われ続けているような状況だ。
 |
以前から続いてきたTencentとの綿密な関係
新型コロナウイルス感染症の流行に際し,欧米各国で発動された厳戒令以降,Ubisoft Entertainmentは多くの社員が週の半分をリモートワークで働けるようにしたが,多くのプロジェクトが遅延してしまい,その遅れを補うために2022年の最盛期には2万人超の従業員を雇用するほどになった。巣ごもり需要にも上手く乗れず,同年9月には資金繰りの悪化からTencent Holdingsから計3億ユーロの投資を受けるが焼石に水だった。
近年の「アバター:フロンティア・オブ・パンドラ」「スカル アンド ボーンズ」「エックスディファイアント」「スター・ウォーズ 無法者たち」といった作品が振るわなかったことは,4Gamer読者であればご存じだろう。唯一,「プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠」は高い評価を受けたがセールスには結び付かず,続編の企画も通ることはなく2024年10月にチームは解散している。
 |
2024年5月には「アサシン クリード シャドウズ」を正式に発表したが,作品の内容やUbisoft Entertainmentの対応が多くの批判に晒されてきたことは,当連載(第799回:「アサシン クリード シャドウズ」から始まった“弥助問題”を考える)などでもまとめている。
2度の発売延期を経て今年3月にリリースされた本作だが,欧米メディアからの高評価に対して,セールスがそれほど伸びたというわけでもないようだ。
「アサシン クリード シャドウズ」がどれだけ成功しようが,もはやUbisoft Entertainmentの株価下落は防ぎようがなく,全株式の9.99%(現在)を保有する大口株主であるTencentによる買収も念頭に入れている――そんなストーリーは2024年10月の時点で伝えられていた(関連記事)。2025年に入り,5年間で85%も資産価値を失うことになった株主が集団訴訟を準備しているという動きもあり,開発資金さえ滞り始めていた同社は,何らかの「出口」を見つけなければならない状況になっていたのだ。
 |
Tencentと言えば,「Arena of Valor」「Call of Duty: Mobile」「Pokémon Unite」といったモバイルゲームから,「デルタフォース」などのFree-to-Playゲームまで統括するTiMi Studio Group,伊津野英昭氏がジョインしたLightSpeed Studiosといった5つの内部スタジオを持ち,「League of Legends」のRiot Games,「Dune: Awakening」のFuncom,「Path of Exiles 2」のGrind Gear Gamesの経営権を100%所有する。まさに世界最大のサードパーティ・パブリッシャだ。
さらにTechland,Fulqrum Publishing,Klei Entertainmentの経営権を掌握し,Supercellの84%,Don’t Nodの42%,Epic Gamesの35%,Bloober Teamの22%,マーベラスの20%,フロム・ソフトウェアの16.25%,KRAFTONの13.87%を保有するという大口株主でもある。もはやゲーム業界にとって,Tencentの投資がなくてはままならないと言ってもいい存在になっている。
これまでUbisoft Entertainmentと築き上げてきた関係や今回の11億6000万ユーロにのぼる投資も,そうした海外戦略の一貫として行われたのは間違いない。
巨額投資による提携は両社にメリット
Ubisoft Entertainmentの発表によると,新たに誕生する子会社は「アサシン クリード」「ファークライ」「レインボーシックス」を主に扱う開発会社となり,Tencentへのロイヤリティと引き換えに,ゲームブランドの知的財産権やクリエイティブコントロールの維持,これらのシリーズのライセンス権を保有する。
11億6000万ユーロの投資を受けて財政が健全化し,今後の開発につなげられるようになったことで,競争力のあるゲームの開発に専念できるというわけだ。
一見すると,Ubisoft Entertainmentが経営権を譲り渡したように見えるかもしれないが,子会社の25%の株式を獲得したTencentは株主総会や決議の開催といった権利を得ただけに留まる。おそらくは「Call of Duty: Mobile」と同じく,「アサシン クリード」「スプリンターセル」といった資産を活用して,“ライセンス”という形でモバイルゲームやFree-to-Playゲームをパブリッシングすることで,ブランド価値を高める狙いがあるのだろう。
なぜ,完全買収が行われなかったのだろうか。イヴ・ギルモ氏は以前から,「クリエイティビティは譲り渡すことができない」と明言してきた。当連載(第476回:Vivendiが仕掛けたUbisoft買収の動き)でも解説したことがあるが,Ubisoft Entertainmentは自国の大手メディアによる執拗な敵対的M&Aに5年越しで打ち勝ち,その経営権を守ったという自負があるのだ。
今回の提携は,新子会社の企業価値(プレマネー)をUbisoft Entertainmentの3.5倍となる40億ユーロまで高めており,その魂を売り渡すことなく経営の健全化に成功したと言える。
 |
Tencentにとっても,もし完全買収に踏み切っていたら,さまざまな地政学的な問題や規制により,これまでの大胆ながらも慎重に中国以外におけるプレゼンスを高めてきた戦略に悪影響が出る可能性は十分にあった。現在の政情を踏まえれば,今回の“控えめ”な投資は国内外にアピールできる人気ブランドを自由にライセンスして利益を上げていく,それと共に企業の存在感を強める賢明で安全な手法だろう。
Ubisoft Entertainmentの株価は上昇する気配もなく,投資家は今回の動きに対して辛口な評価をしていることは間違いない。しかし,Ubisoft Entertainmentというブランドを守るために戦い続けてきたイヴ・ギルモ氏らが諦めることはないはずだ。
おそらく新会社からUbisoft Entertainmentに間接的に投資する形で,Ubisoft Montpellierが開発中の「Beyond Good and Evil 2」をはじめ,Massive Entertainmentの「ディビジョン」新作,Ubisoft Milanが主導するという「Rayman」新作など,知的財産権が移行していないタイトル群が生み出されるだろう。多くのファンを抱える「ウォッチドッグス」や「ANNO」なども,そう簡単に手放していいわけがない。
Tencentによる大口投資を受け入れたことにより,ギルモ兄弟は新たな戦いのための槍を得た。ハラスメント問題に揺れて多くの幹部を失うことになった体制と,その反動として「DEI(多様性,公平性,包括性の略称)に傾倒している」とゲーマーから揶揄される社風を改革し,「オリジナルの創造性により,プレイヤーの人生を豊かにする」という初心に戻る機会になるかもしれない。
近々アナウンスされる子会社の続報を楽しみにしたいところだ。
 |
著者紹介:奥谷海人
4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。
- この記事のURL: