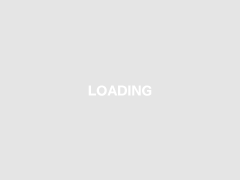ニュース
[CEDEC 2006#04]恋愛シムを通して,ゲーム性やクリエイター/パブリッシャ関係を再考する
 |
それはさておき,そこに登場した4人のパーソナリティは,なかなか派手な顔ぶれ。東京大学 大学院情報学環 コンテンツ創造科学産学連携教育プログラム 吉田正高氏の差配で集まったのは,サブカル評論で名高い哲学者の東 浩紀氏と,PCからゲーム機への移植事業で名高いアルケミストの代表取締役 浦野重信氏,そしてベックの芝村裕吏氏だ。芝村氏に関しては“アルファ・システムの”人としてご記憶の人も多いかと思うが,氏は現在,バンダイナムコグループの傘下にあるベックに所属する。
一応パネルディスカッションの形で行われた今回のセッションだが,実質的にはそれぞれ立場の異なる3人によって,恋愛シミュレーションゲームが持つ論点が浮き彫りにされた,というのが最も端的な説明だろう。最初に吉田氏が恋愛シムの歴史的展開をざっと整理し,東氏は恋愛シム(氏の分類概念としては美少女ゲーム)の“ゲーム性”を抽出,アルケミスト 浦野氏が作品移植の実際について語り,芝村氏がゲーム開発の立場からこれらを補足して議論を深める,という体裁になっていた。
あまり議論らしい議論のない複数講演ではあったが,論点として興味深かった点を中心に,セッション内容をお届けしよう。
 |
 |
■総「萌え」化の時代
 |
そして1980年代中には同じく,アダルトゲームの市場が成立/拡大,1990年代初頭には批判世論が盛り上がって自主規制団体の成立にいたるといった経緯を説明した。続けて,その時期以降,恋愛シムは多様化を続け,現実に近いシチュエーションのみならず,SF/ファンタジーからダークファンタジーへ,他方でライトノベル的展開を遂げた作品が現在のセカイ系に繋がっていくなど,基本的な系譜関係を整理した。
 |
 |
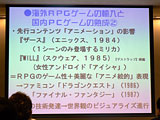 |
 |
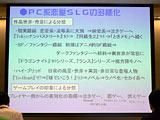 |
そうしたなかで,ゲーム機における恋愛シム展開も1995年にスタートし,1996年から1997年にかけてピークを迎えたとする。やがて1997年の「センチメンタル・グラフティ」を境に,ゲームそのものより関連グッズがもてはやされる状況がはっきりする。そして氏はこれをゲーム性喪失の嚆矢と見なす。
2002年以降におけるオンラインゲームのヒットと,2000年以降の同人ゲームの隆盛,はたまたここ1,2年における伝統的少女漫画の人気復活やライトノベル市場の盛り上がりといった周辺事情の説明も含めつつ,氏は恋愛シムに限らずエンターテイメントの現状を「総萌え化」と表現する。そして,これはいたって常識的な見解といえようが,記号に分解されたキャラクターは差別化点を失う宿命にあり,この消費形態の限界性に関する危惧を表明した。
話のとっかかりとして,全般的な状況を整理したものであるから,この時点で明確な論点提示が行われなかったのは無理からぬところか。
 |
 |
 |
 |
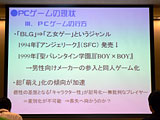 |
 |
■美少女ゲームを通して,ゲーム性を再定義する
 |
氏が考察対象とするのは,Leafの「雫」の影響により出現した,テキストと立ち絵に依存するシナリオ分岐型恋愛アドベンチャーである。氏は便宜上これを狭義の「美少女ゲーム」と呼ぶが,この定義にはファンによる需要と消費の形も勘案されていると思われる。後で吉田氏も指摘したとおり,それ以前の作品,例えば「同級生2」のファンコミュニティでは,まだ一般的な“ゲーム性”に近い「早解き」が関心対象だったのに対し,Leaf作品以降では,まさにキャラクターを愛でるといった動きが明確化してくるからである。
そうした美少女ゲームの展開を足早に追いつつ,氏はゲームのインタフェースが驚くほど変化していないことに着目する。キャラクターグラフィックス部分がアニメに近い挙動を実現しても,テキストはテキストのままだ。氏はそれを,近年にいたるいくつかの実例を挙げつつ説明した。
そして,ノベルゲーム「ひぐらしの鳴く頃に」の作者たる竜騎士07氏の発言などを追いつつ,おそらくはこのインタフェースそのものが,創作をインスパイアする,つまりこの形で作品を作りたくなる何かであり,その何かこそが「ゲーム」と呼ばれるゆえんであると結論づける。そのうえで氏は,ファン達がこの形に「ゲーム」を見いだす理由として,彼らが既存のゲーム性定義以外のところに“ゲーム性”を見ている可能性を想定,その中身を
・マルチエンディングな物語の可能性
・ユーザーコミュニティの空間
という要素から読み解こうと試みる。
氏自身述べるとおり,「ライトノベルは小説じゃない」「萌え漫画はつまらない」式に「美少女ゲームはゲームじゃない」と片付けるのは簡単だし,氏が抽出したインタフェースにしたところで,PCを道具立てに使った安価なアニメ代用品制作手法だと,斬って捨てることもできよう。
しかし,それではせっかく育ってきた独自の手法が持つ可能性を,まるで顧みないことになってしまう。つまり,物語の展開やエンディングの形,はたまたプレイヤーコミュニティのあり方などによって,ゲーム性という言葉に込める意味が再定義されるべきではなかろうかと,そういう話なのである。そして,このインタフェース/制作手法の持つ神秘の解明が,その糸口になるはずというのが,とりあえず氏の現在の関心であったようだ。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
■クリエイターと移植業者が仲良くやっていくこと
 |
氏が強調したのは,とにかくクリエイター側と「仲良くやっていく」こと。それはアルケミストの目標でもあり,クリエイター側への希望でもある。氏の説明内容の概略は,スライドの写真で確認してほしい。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
時間の都合もあってあまり活発な意見の応酬がなかったのだが,その中でやや生臭いやりとりの例を挙げるならば,アルケミストが担当する「ひぐらしの鳴く頃に」の移植で,原作になかったストーリー上の分岐が付け加えられている点についてだろうか。
吉田氏がアルケミスト浦野氏に,この話題について水を向けると,浦野氏の回答は「もともと作者の方が一人で作っていることもあって,『ひぐらしの鳴く頃に』という作品の形には限界がありました。それにアルケミストが関わることで,作者の方がむしろ望んでいた形を,実現したのです」というものだった。
実際,作品とは何であるか(創作物? 商品?)を考えるとき,これはたいへん微妙な問題になる。作者の意向,移植業者の見解,それを受け取るファンの感情が,常に一致しているとは限らないからだ。
セッション本来の文脈に沿って,移植の問題として考えるならば,浦野氏が強調する「仲良くやっていく」ことの重要性に,疑いの余地はない。だが一方で,コンテンツ産業がアテンション・エコノミー(電子情報=作品そのものはコピー可能なので価値を失っていき,むしろ注目され,話題にされる場面が商売になっていくとする,今後の産業推移予測)の波に呑まれていくとすれば,作品を作るクリエイターと,作品を世に出すパブリッシャの立ち位置や利害は,対立をはらみつつ大きく変化していくはずだ。権利者であると同時に作品の生みの親でもあるクリエイター,提案型興行主としてのパブリッシャは,ときに同床異夢の関係になるだろう。
一つのゲーム作品にとって,移植や関連製品開発が持つ商業的重要性は,今さら強調するまでもない。今回,クリエイター/パブリッシャ関係の話はそれほど突き詰められなかったが,とりあえず現時点における移植者(パブリッシャ)側の偽らざる実感を聞けたという点では,それなりに興味深い話だった。(Guevarista)
 |
 |
- この記事のURL:







![[CEDEC 2006#04]恋愛シムを通して,ゲーム性やクリエイター/パブリッシャ関係を再考する](/image/rss_noimage_w2400.png)