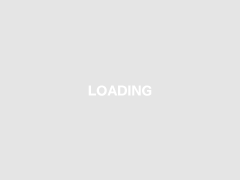Kingston Technology(以下,Kingston)は,CES 2020の期間中,サブ会場の高級ホテルにプライベートブースを設けて,ゲーマー向け製品ブランド「
HyperX」の新製品を招待者限定で披露していた。
本稿では,それら新製品の中から,国内でも注目を集めそうなヘッドセット「
HyperX Cloud Flight S」(以下,
Cloud
Flight
S)と,スマートフォン向けアクセサリ「
HyperX ChargePlay Clutch」(以下,Charge
Play)の2製品を紹介しよう。
Cloud Flight S
Qi対応の充電機能を備えたワイヤレスヘッドセット
最初に紹介するCloud Flight Sは,2018年に国内発売となったHyperX初のワイヤレスヘッドセット「
HyperX Cloud Flight」を大きく進化させたPCおよびPlayStation 4(以下,PS4)対応のヘッドセットである。
Cloud Flight S
 |
Cloud Flight Sにおける第1の特徴は,非接触充電技術である「Qi」(チー)対応の充電機能を内蔵することだ。Qi対応の充電器は,とくにスマートフォン用としてさまざまな物が市場に出回っているが,近年はゲーマー向けマウスパッドにもQi対応製品が増えている。そうしたQi対応充電器の上に,Cloud
Flight
Sの左イヤーカップ(エンクロージャ)を載せておくだけで,充電を行えるわけだ。
Cloud Flight Sの左イヤーカップ。この中にQi対応充電機能が組み込まれている。上下左右にある丸い凹みは,後段で説明するタッチセンサーだ
 |
写真のように,左イヤーカップをQi対応充電器の上に載せると,自動で充電が行われる
 |
もう1つの特徴は,左イヤーカップに組み込まれたタッチボタンによる操作が可能な点にある。
タッチボタンは,左イヤーカップの上下と左右にある丸い凹みの中にあり,指で軽く触れるだけで,ヘッドフォンやマイクの音量調整,メディアアプリケーションの再生や早送り・早戻しといった操作が行える。各ボタンへの機能割り当ては,HyperX製品向けの統合設定ソフトウェア「HyperX NGENUITY」(以下,NGENUITY)でカスタマイズできる仕組みだ。
NGENUITYでタッチボタンに割り当てる機能を選んでいる様子
 |
イヤーカップを90度回転させた状態
 |
ヘッドセット本体についても触れておくと,50mm径のネオジムドライバーを採用し,PCやPS4と2.4GHz帯の電波を使う独自方式のワイヤレス接続が可能となっている。また,7.1chバーチャルサラウンドサウンド再生機能を備えているのも特徴だ。
左右のイヤーカップは,アームとの取り付け部分で90度回転して,魚の開きのような持ち運びやすい形状に変形できる。
左イヤーカップ(左)には,電源ボタンやバーチャルサラウンド機能のオン/オフ切り替えボタン,充電用のUSB Micro-B端子,着脱可能なブームマイクの接続端子が並んでいた。一方,右イヤーカップには,音量調整ダイヤルがあるだけだ(右)
 |
ChargePlay
Qi対応の充電機能付きスマートフォン用グリップ
次に紹介するスマートフォン用アクセサリのChargePlayは,スマートフォンを挟み込むように取り付けるグリップにモバイルバッテリーとQi対応充電器の機能を組み込んだ周辺機器である。世界市場では2020年第2四半期に発売の予定で,北米市場向けのメーカー想定売価は
59.99ドル(税別)とのことだ。
ChargePlayの本体(左)。HyperXのシンボルマークが描かれた部分を挟み込むように,可動式のグリップが付いていた。Qiの充電機能は,シンボルマーク部分にある。右はグリップを最大まで広げた状態だ
 |
 |
ChargePlayは,かなり大きめのスマートフォンでも取り付けられるようになっており,筆者所有の「
Galaxy Note10+」も問題なく取り付けられた。ただ,グリップ部分は相応に幅があるため,装着した状態で画面左右に表示されたUIを操作するには,ちょっと慣れが必要かもしれない。
Galaxy Note10+をはめ込んだ状態のChargePlay
 |
左手でグリップを持ちながら撮影してみた。「アズールレーン」のように,端末の画面アスペクト比によっては,画面端から少し離れたところに仮想ゲームパッドが表示されるゲームの場合,慣れるまで少し操作しにくかった
 |
先述したとおり,ChargePlayの中央部分にはQi対応充電器が組み込まれている。そのため,背面の中央あたりにQiの受電用アンテナを備えているスマートフォンであれば,iPhoneであろうがAndroid端末であろうが,取り付けるだけで充電しながら操作することが可能だ。
ChargePlayの背面。中央部のモバイルバッテリーは着脱可能だ
 |
ChargePlayの上側面。モバイルバッテリー部分には,充電用のUSB Type-Cポートと給電用のUSB Type-Aポートが備わっている
 |
一方,Qiに対応していないスマートフォンの場合,ChargePlay背面に取り付けるモバイルバッテリー部分に給電用USB Type-Aポートがあるので,付属のUSB Type-A to Type-Cケーブルを使うことで,有線接続にはなるが充電しながらスマートフォンを使用可能となる。
ちなみに,ChargePlayはスマートフォン用が初の製品ではなく,北米市場では,2019年11月にNintendo Switch(以下,Switch)用のChargePlayをすでに発売している。SwitchにはQi対応充電機能がないので,グリップ下側にあるUSB Type-Cポート経由で給電する仕組みだ。
Switchに取り付けた状態のSwitch用ChargePlay
 |
Switchの本体裏側にあたる部分は,キックスタンドとなっていた(左)。左右グリップは,ChargePlay本体から取り外し可能で,それぞれにJoy-Conを取り付けて合体させると,小型のゲームパッドに早変わりする(右)
 |
 |
単純に充電しながらゲームをするなら,モバイルバッテリーを別途用意すればいいが,とくにスマートフォンを横持ちするときにケーブルが気になるというケースがある。グリップ側にモバイルバッテリーを備えるだけでなく,Qiに対応したChargePlayであれば,よりゲームに集中しやすいといったメリットがあるかもしれない。モバイルバッテリーを別途用意しない形で,ゲームを長時間プレイしたいという人には,魅力的な周辺機器と言えるのではないだろうか。















 HyperX
HyperX