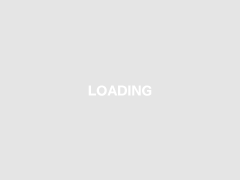イベント
[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり
![画像集#043のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/043.jpg) |
![画像集#042のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/042.jpg) デジタル・フロンティア CG制作部 ディレクター 土井 淳氏(左),テクニカル・ディレクター 野澤徹也氏(右) |
「バイオハザード ダムネーション」のCG制作期間は約12か月で,2011年9月から2012年8月まで行われた。スタッフ数は俳優/声優を含めると,延べ450人(デジタル・フロンティア社内スタッフは200人)と,かなり規模の大きいプロジェクトだ。
大まかなワークフローは,シナリオ作成,ロケハン,画コンテ,モーションキャプチャ,アニマティクス,エフェクト,レンダリング,合成,カラコレ,3D化といった流れだが,前作「バイオハザード ディジェネレーション」と大きく異なったのは,ロケハンを行ったことと,3D立体視に対応したことだという。
![画像集#001のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/001.jpg) |
![画像集#002のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/002.jpg) |
本講演では,このワークフローを踏まえて,土井氏によってモーションキャプチャの説明が行われた。前作の制作を行っていたときよりもデジタル・フロンティアのスタジオ設備が充実しており,カメラが50台から100台に増えただけでなく,カメラ自体も性能が良いものに置き換えられており,前作の作成時と比べると全体的な取り込み精度が8倍になったという。また顔の表情をキャプチャする専用の設備もあるため,顔の細かい動きなども取り込めるようになったそうだ。
同社のスタジオでは,顔,指,体をまとめてキャプチャするパフォーマンスキャプチャも可能だが,本作の制作においては,精度を優先して,体は体,顔は顔,指は指と,それぞれ個別にキャプチャしたという。
![画像集#003のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/003.jpg) |
また,本作のモーションキャプチャで特徴的だったのは,四足歩行のクリーチャー「リッカー」の動きも,人が演じたことだ。もちろん人間とは根本的に形が異なるので動きをそのまま使うというわけにはいかず,実際には3割程度しか使用しなかったが,人とリッカーが入り乱れるアクションシーン作成時のタイミング調整などに役だったそうだ。
デジタル・フロンティアのスタジオでは20人まで同時にモーションキャプチャが行えるようになっており,本作では最大9人が同時に動くというシーンが撮影された。個別に撮って対応することもできるが,同時に撮ることによって臨場感が増し,動きの関連性の精度が上がるのだという。
また,通常のシーンでは指の動きは3本までしか認識させていないそうだが,銃に弾を込めるといった場面では,それ専用に5本分の撮影を行ったそうだ。
続いて話はキャクターメイキングへ。本作のキャクターは,恩田尚之氏が描いた線画をもとに3D化された。また,衣装の制作では,本作の監督である神谷 誠氏が私物を持ち込んで自ら着込み,それをベースにキャラクターを描いていったそうだ。というのも,軍事用品は徹底して使いやすさを重視して作られているため,デザインありきで描いてしまうとどうしても嘘っぽくなってしまうのだ。ポケットの位置一つにもこだわるからこそ,本物らしくなるというわけだ。
また,日本人が人物のレタッチを行うと,どうしても日本人っぽさが出てしまうため,欧州のアーティストがいるプロダクションに依頼したというのもこだわりの一つだろう。
![画像集#004のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/004.jpg) |
![画像集#005のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/005.jpg) |
![画像集#006のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/006.jpg) |
![画像集#010のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/010.jpg) |
次の話題はライティング(照明設計)だ。本作におけるライティングのテーマは,臨場感を最大限に出すことで,時間経過も緻密に表現するように心がけられた。前作のライティングは,朝,夜,室内という3パターンのみだったが,本作ではさらに細かい設定がなされている。具体的には,3時,5時,6時といったように時間帯を分け,それぞれを細かく描くことで,作品全体の臨場感をアップさせたそうだ。
また,実際にどういったライティングにするかというイメージをスタッフ間で共有するために,イメージボードが描かれた。本作は1250カットで構成されているそうだが,その約1割に相当する130カットものイメージボードを作成したという。これによって,イメージボードを描くという別の作業が発生したわけだが,その存在によって作業効率が上がるなど,メリットは大きかったようだ。
ちなみに,ライティングチームは10人ぐらいで構成されており,1か月くらいかけて,ライティングに関する作業だけを行っていたというのだがら,頭が下がる。
![画像集#013のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/013.jpg) |
![画像集#014のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/014.jpg) |
背景作成では,より現実感を表現するために,実際にウクライナまで行くという,ロケハンが実施された。これにより「想像するだけでは無理がある,生活感のようなものが表現できた」と土井氏は語った。
いわゆる雰囲気を本物らしくするだけでなく,建物/部屋の一つに対しても細かい設定を用意し,リアリティを出している。今回例にあげられた部屋は4000万ポリゴンで描かれているが,これは本作のなかでは少ないほうで,背景によってはポリゴン数が4億を超えているという。
![画像集#016のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/016.jpg) |
![画像集#017のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/017.jpg) |
![画像集#018のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/018.jpg) |
![画像集#019のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/019.jpg) |
また,本作は3D立体視映画ということで,奥行きをいかに出すのかというのも重要なテーマだった。それを踏まえて,本作の制作ではリニアワークフローが採用された。これによって,暗部の階調,ディテールを潰さずに表現でき,現実により近い形で合成できるのだ。リニアワークフローを採用すると,マスターモニターと同等の色調で作業できることも利点の一つで,より現実に近い形のコンポジットで出力できたそうだ。なお,本作では「Adobe After Effects」が使用されたが,処理速度を考慮して32bitでの合成を断念し,16bitで作業が行われた。
![画像集#025のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/025.jpg) |
![画像集#026のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/026.jpg) |
長編フルCG映画を作るうえで大切なこと
続いて野澤氏によって,長編フルCG映画を作るうえでのプロジェクト管理方法などが説明された。本作ぐらいの規模の映画になると,プロジェクト全体のデータ容量は100TB以上になり,レンダー関連データだけでも30TBを超えたという。また,冒頭で述べられたように数百人規模の人間が動いているプロジェクトなので,効率的なスケジュールを組まないと,一つの問題で多くの人が足踏みをするということになってしまう。全スタッフが同じ目標を共有できていないと,自分達が前に進んでいるのかどうかすらも分からなくなりがちだ。
![画像集#028のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/028.jpg) |
![画像集#029のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/029.jpg) |
本作では新たな挑戦として,前作よりもクオリティを飛躍的にアップさせることが目標に掲げられた。過去に制作した作品で培ったノウハウを取り入れつつ,新たなツールも積極的に使い,ロケハンだけでは補えない部分は,現地スタッフ(他社スタッフ)に制作に加わってもらうことでカバーした。現地の人の手が入ることによって,現実感は格段にアップしたそうだが,デジタル・フロンティアで使っている3Dソフトが「Maya」だったのに対し,現地の会社が「3dsMax」を使用していたためにデータの受け渡しで問題が発生してしまう。そこで異なるCGソフト間の垣根を越えるオープンソースのファイルフォーマットであるAlembicを使うことになったが,Excortexという会社が5ライセンスを399ドルで販売しているものは予算的に現実的ではないため,デジタル・フロンティアで「Alembic for 3dsMax」というものを開発するという力技に出て,この問題を解決した。
ちなみに,Alembic自体がオープンソースということもあり,デジタル・フロンティアは「Alembic for 3dsMax」の無償配布を行っている。興味のある人はデジタル・フロンティアの公式サイトにアクセスしてダウンロードしてほしい。
![画像集#035のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/035.jpg) |
![画像集#036のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/036.jpg) |
続いて話はCG制作において“苦行”といわれるレンダリングに。長編フルCG映画で使用する素材数は膨大で,無計画なレンダリングは必ず問題を引き起こすと野澤氏は語る。
レンダリングにおけるミスは,アセットの更新情報が伝わっていない状態で古いバージョンのまま実行してしまったり,膨大な量の素材を把握できていなかったりといった,ヒューマンエラーによって生まれることが多い。これを解消するためにデジタル・フロンティアでは,「RenderPackage」というものを生み出した。これは異なるファイルサーバーで管理されているアセット,テクスチャなどを相対パスに変換したり,タイムスタンプで比較したり,バージョンをロックしたりしつつ,一つのパッケージとして書き出すというもの。RenderPackageをするために内製のブラウザも開発し,手軽にパッケージ化が進められるように工夫したという。またデータベースと連動し,進捗状況をウェブブラウザベースで管理できるシステムも構築した。
![画像集#037のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/037.jpg) |
![画像集#038のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/038.jpg) |
![画像集#039のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/039.jpg) |
![画像集#040のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/040.jpg) |
RenderPackage化を導入したことで,複数のレンダーファームへの移動準備やバックアップが容易になったほか,レンダリングしたパッケージの特定が楽になったという。また,パッケージ化がクッションとなって,致命的なエラーの発生を抑えるという効果があったほか,小分けにすることでレンダーの状況確認がやりやすくなるというメリットもあったそうだ。
と,いいこと尽くめのようなRenderPacage化だが,落とし穴もある。例えば,Mayaの仕様で相対パス化できないものがあったり,ツールの更新タイミングを間違えると“ゴミパッケージ”が量産されてしまったりするという。また,管理がずさんだとRenderPacage化をする以前よりも混乱してしまうなど,結局は人が努力しないといけない。それでもRenderPacage化のメリットは大きいと野澤氏はアピールしていた。
![画像集#041のサムネイル/[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/041.jpg) |
今,データ容量はテラからペタへと移り変わろうとしている。野澤氏は,時代の流れに逆行することなく,増えていくデータにとことん向き合っていくとデジタル・フロンティアの姿勢を語り,講演を締めた。
「バイオハザード ダムネーション」公式サイト
「デジタル・フロンティア」公式サイト
- この記事のURL:







![[CGWORLD 2012]「バイオハザード ダムネーション」のメイキングレポート。デジタル・フロンティアが語る長編CG映画の作り方とこだわり](/games/000/G000000/20121030023/TN/044.jpg)